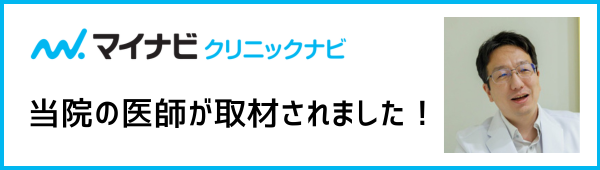2021/11/25

小さなお子さんは目についたもの、気になったものを口で確かめる習性があります。
これは普通のことで成長過程のうえでとても大切なことです。
しかし口にくわえて舐める程度であれば問題なく済むものもありますが、誤って飲んでしまう可能性もあります。
今回は誤って飲んでしまったときに気を付けるものや対処方法などを紹介していきます。
■誤飲とは?
そもそも誤飲とはなにかというと、漢字の通り「誤って飲んでしまう」ことです。
子どもの喉の太さは3歳児で直径約4cmです。
これよりも小さいものだと喉に入ってしまうということです。
また家庭の中には固形物だけではなく、液体状のものなどもありますので細心の注意が必要になってきます。
■気を付けるべきもの
では家庭で気を付けるべきものを確認していきましょう。
子どもが誤飲しやすいもので代表的なものは、
・ボタン
・電池
・薬
・タバコ
・クレヨン
・小さなおもちゃ(人形など)
・保冷剤
・チョコレートなど小さな包み紙
などが挙げられます。
ボタンなどは衣類についている場合も少なからずあり、知らないうちに引っ張って取れてしまい、口に運んでしまうこともあります。
大人の不注意でタバコや電池など、手に届かないだろうと思っても届いてしまい口に入れてしまうこともあります。
確実に届かない場所におくようにしましょう。
■吐かせていいものと悪いもの
では口に入れて誤嚥してしまったことに気づいたとき、どうしたらよいでしょう。
焦って指をいれて胃内容物を吐かせる行動をする方もいますが、いったん誤飲したものを確認しましょう。
中には吐かせてはいけないものもあります。
早急に吐き出させたいものとしては、
・たばこ
・ゴキブリ殺虫剤(ホウ酸団子)
・防虫剤
・医薬品
などはすぐに吐き出させないと人体に影響を与えてしまいます。
吐かせてはいけないものとして、
・電池類
・灯油
・ベンジンなどの化学物質
・小さなおもちゃなど
があります。
これを吐き出させると、再度食道を通ります。
誤飲物を往復させることで喉に再度薬液が付着して炎症を進めたり、傷をつけることになります。
このようなものを飲み込んだ時には必ず夜間でも受診をしましょう。
・化粧品
・シャンプー
・芳香剤
・粘土
などは比較的刺激が弱いものになります。
翌日まで様子を見て、腹痛などの体調不良が出たら夜間でも受診をおすすめします。
■家庭でできる対応
では最後に家庭でできる対処方法を紹介します。
誤飲した場合には、意識・呼吸・顔色・嘔吐の有無を観察していきます。
もしも口の中を確認して、誤飲したものが見える場合は指でかき出しましょう。
何を飲んだかというのが治療の内容を決めます。
救急隊に連絡する際や受診して医師へ伝えるときには、何をどのぐらい飲んだのかを伝えましょう。
洗剤や漂白剤などボトルがあると思いますので、成分表が書いてある容器を一緒に持参してください。
対処方法がわからないときには、下記へ連絡して相談してみれば適切な対処を教えてくれます。
公益社団法人日本中毒情報センター(中毒110)
・大阪中毒110番 072-727-2499
・つくば中毒110番 029-852-9999
タバコ専用ダイアル 072-726-9922
もしも判断に困った場合には「#8000」に電話しましょう。
厚生労働省が行っている子ども医療電話相談事業でお住まいの地域の相談窓口に自動転送されます。
小児科医や看護師に症状や対応を相談することができ、アドバイスができます。
救急車を呼ぶかどうかなど困っているときや、子育てが初めての方などはぜひ使ってみてくださいね。
厚生労働省「子ども医療電話相談事業」詳細はこちら
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/10/tp1010-3.html
参考資料;山口県小児科救急医療ガイドブック
(監修:山口県小児科医会 制作:山口県健康福祉部医療政策課医療対策班)