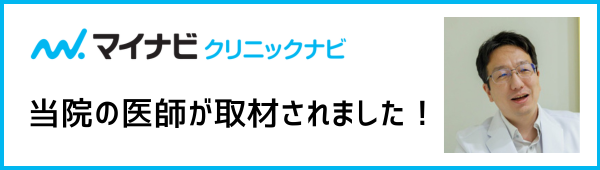2025/01/20

「痛み止め」と一口に言っても、様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。上手に使えば、つらい痛みを和らげ、より快適な生活を送る手助けとなります。
しかし、自己判断で使用したり、過剰に服用したりすると、副作用やオーバードーズ(薬の飲みすぎ)といったリスクも伴います。必ず医師や薬剤師の説明をよく聞き、用法・用量を守って正しく使用しましょう。
今回は、代表的な痛み止めの種類と特徴を、薬剤師の視点からわかりやすく解説します。
1. 非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)
◆特徴:
・炎症を抑える効果があり、軽度〜中等度の痛みによく用いられます。
・炎症を伴う痛み(例:関節痛、生理痛、筋肉痛など)に特に効果を発揮します。
・市販薬としても広く販売されています。
◆代表的な成分:ロキソプロフェン、イブプロフェン、アスピリンなど
◆注意点:
・副作用として胃腸障害(胃痛、吐き気など)を起こしやすいことが知られています。そのため、胃薬(胃粘膜保護薬)と併用されることがあります。
・腎機能障害のある方は、使用前に医師や薬剤師に相談してください。
・長期連用は避け、漫然と使用しないようにしましょう。
2. アセトアミノフェン
◆特徴:
・痛みだけでなく、熱を下げる効果もあります。
・インフルエンザや新型コロナウイルス感染症(COVID-19)など、発熱を伴う病気の際に処方されることが多いです。
・非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)と比較して、胃腸障害を起こしにくいとされています。
◆代表的な商品名:カロナール、タイレノールなど
◆注意点:
・高用量を長期間服用すると、肝障害のリスクがあります。
・必ず医師または薬剤師の指示に従い、用法・用量を守って服用してください。
・市販薬を併用する場合は、成分が重複しないように注意が必要です。
3. オピオイド(医療用麻薬)
◆特徴:
・非常に強力な鎮痛作用があり、主にがん性疼痛など、強い痛みを伴う場合に用いられます。
・痛みを緩和することで、Quality of Life(生活の質)の維持・向上に貢献します。
◆誤解と注意点:
・「麻薬」と聞くと、依存性や精神的な影響を心配される方もいるかもしれません。しかし、医療用麻薬は医師の指示に従って使用すれば、依存症になる可能性は低いとされています。
副作用として、眠気、便秘、吐き気などが現れることがあります。
がん末期の患者さんに使用すると、眠気が強くなり、状態が悪化するのではないかと心配される方もいますが、オピオイドの使用によって寿命が短くなることはありません。
自己判断での使用は絶対に避け、医師の指示に従ってください。
4. 合成オピオイド
◆特徴:
・医療用麻薬(オピオイド)ほどの強い鎮痛効果はありませんが、中等度の痛みに対して効果が期待できます。
・非麻薬性であり、依存性は低いとされています。
・痛みが続くことで生活の質(QOL)が著しく低下する場合は積極的に使用を検討しましょう。
◆代表的な薬剤:トラマドール
◆注意点:
・眠気や吐き気などの副作用が出ることがあります。
・運転や危険な作業を行う際は注意が必要です。
5. 神経障害性疼痛治療薬
◆特徴:
・糖尿病性神経障害や帯状疱疹後神経痛など、神経の損傷や機能異常によって生じる痛み(神経障害性疼痛)に効果を発揮します。
◆代表的な薬剤:プレガバリン(リリカ)、ガバペンチン
◆メカニズム:
これらの薬剤は、神経の過剰な興奮を抑えることで痛みを緩和します。痛みの原因そのものを治すわけではありません。
◆その他:
がん性疼痛など、中枢性の痛みには、上記の薬剤ではなく、医療用麻薬(オピオイド)などが用いられます。効果が現れるまでに時間がかかることがあります。
6. 筋弛緩薬
◆特徴:
・筋肉の緊張を和らげることで、痛みを軽減します。
・脳性麻痺による筋緊張の緩和や、重度の肩こりなどに用いられます。
◆代表的な薬剤:メトカルバモール、エペリゾン
◆注意点:
・眠気やふらつきなどの副作用が出ることがあります。
・車の運転や危険な作業を行う際は注意が必要です。
痛みは体からのSOS。我慢せずに、まずは病院へ
痛みは、体からの危険信号です。痛み止めは、あくまで症状を和らげるためのものであり、病気そのものを治しているわけではありません。
漫然と市販薬を使用し続けるのではなく、痛みが続く場合は、必ず医療機関を受診し、適切な診断と治療を受けてください。
大切なこと:
・自己判断で薬を使用せず、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
・用法・用量を守って正しく服用しましょう。
・副作用が現れた場合は、すぐに医師または薬剤師に連絡しましょう。
・痛みが続く場合は、我慢せずに医療機関を受診しましょう。
免責事項:
このコラムは、一般的な情報提供を目的としており、医学的なアドバイスを提供するものではありません。ご自身の症状については、必ず医師または薬剤師にご相談ください。