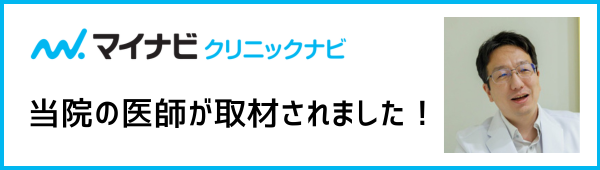2025/06/20
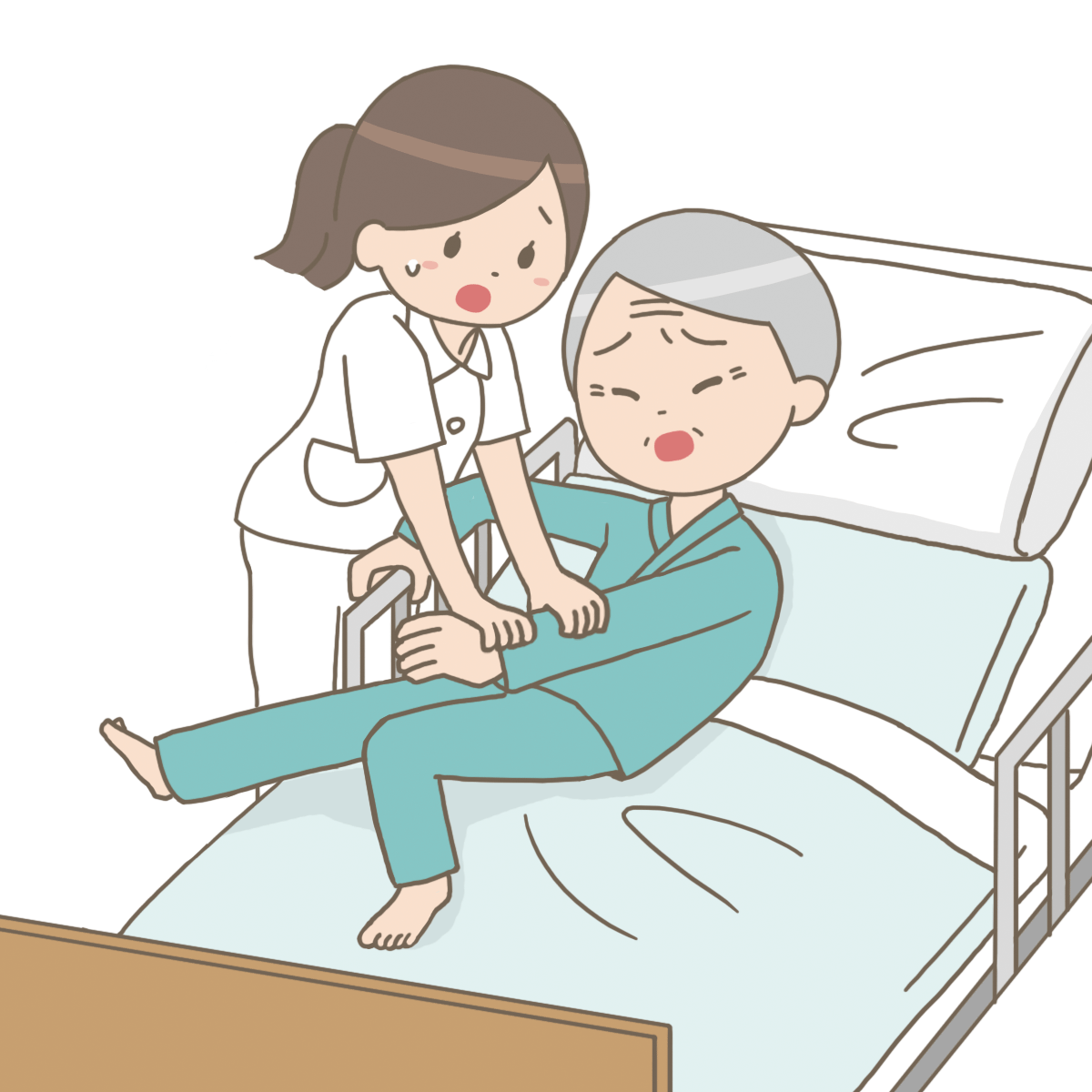
自宅で介護をしていると、思うようにいかないことや、時間に追われて感情的になってしまうこともあるでしょう。特にご家族を介護している場合は、つい強い口調になったり、突き放すような態度をとってしまうこともあるかもしれません。
しかし、介護者の行為が「虐待」にあたるかどうかは、第三者が判断することになります。そのため、介護者は常に客観的な視点を持つことが重要です。
今回は、虐待の中でも特に問題となりやすい「身体拘束」に焦点を当て、身体拘束を行う際に必ず守るべき原則について解説します。
1.虐待とは、人の尊厳を奪う行為
そもそも虐待とは、介護を受ける側の人の尊厳や権利を侵害する行為を指します。
殴る、蹴る、罵声を浴びせるなどの行為はもちろんのこと、「動かないで!」「立たないで!」などと強い言葉で動きを制限することも、言葉による拘束の一種です。
人の尊厳や権利は、法律によって保障されています。介護者だからといって、人の権利を奪うことは決して許されません。
2.例外的に認められる身体拘束
原則として、身体拘束は虐待にあたります。しかし、緊急性が高い場合など、やむを得ない状況においては、例外的に身体拘束が認められるケースもあります。
後述する「身体拘束の三原則」を遵守し、本人やご家族への十分な説明と同意を得るなどの適切な手順を踏めば、法的に罰せられることはありません。
ただし、身体拘束はあくまで最終手段です。可能な限り身体拘束をせずに済むように、あらゆる方法を検討することが重要です。
3.身体拘束を行う際の3原則
身体拘束を行う際には、以下の3原則を必ず守らなければなりません。
①緊急性:生命や身体に重大な危険が及ぶ可能性があり、緊急に身体拘束を行う必要がある。
②非代替性:身体拘束以外に、事故を防止するための有効な手段がない。
③一時性:身体拘束は、必要最小限の時間に限定して行う。
上記の3原則を満たさなければ、身体拘束は認められません。
具体的には、以下の点を常に意識する必要があります。
・なぜ身体拘束を行う必要があるのか
・身体拘束以外に、有効な手段はないのか
・身体拘束を行う必要性がなくなった場合、速やかに解除できるか
4.虐待かどうか判断に迷ったら、まずは相談を
もし、ご自身の行為が虐待にあたるかどうか判断に迷ったり、介護方法について悩んだりした場合は、ためらわずに市区町村の相談窓口や地域包括支援センターなどに相談してください。
誰かに相談することで、気持ちが楽になったり、新たな解決策が見つかることもあります。
5.まとめ:身体拘束は最小限に、安心できる介護を
身体拘束や虐待は、決してあってはならないことです。しかし、介護の現場では、やむを得ず身体拘束が必要となるケースも存在します。
本当に身体拘束が必要な場合は、本人やご家族に十分な説明を行い、同意を得た上で、上記の3原則を遵守し、必要最小限の時間に限定して実施するようにしましょう。
身体拘束を正しく理解し、適切に行うことで、介護を受ける方も、介護をする方も、安心して生活できる環境を目指しましょう。