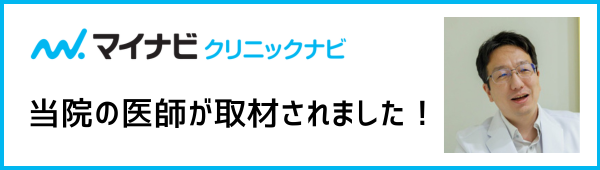2025/01/10

在宅療養を決めたものの、何から始めれば良いか分からず不安に感じる方もいるのではないでしょうか。医療、介護、住環境、経済面、精神的な負担、そして利用できる社会資源…。在宅療養には様々な側面があり、事前に情報を集めておくことが大切です。知っているか知らないかで、その後の負担は大きく変わってきます。
1. 医療面:訪問診療・看護も視野に
原則として、かかりつけ医の診療所への通院が基本となります。しかし、通院が難しい場合や、日常的に医療処置が必要な場合は、訪問診療や訪問看護を検討しましょう。まずは担当のケアマネジャーに相談してみてください。
2. 介護:地域のサポートを頼ろう
療養生活では、介護が必要になる場面も多くあります。核家族化が進み、介護未経験の方も少なくないでしょう。地域によっては介護教室が開催されていたり、訪問介護員(ホームヘルパー)が介護方法を教えてくれる場合もあります。困ったことがあれば、積極的に参加・相談してみましょう。
3. 住環境:福祉用具の活用と住宅改修
介護は全て人の手で行う必要はありません。ご本人が持っている力(残存機能)を最大限に活かすことが大切です。手すりの設置や段差の解消などは、ご本人の自立を助け、介護者の負担を軽減します。 福祉用具のレンタルや購入、住宅改修には介護保険が適用される場合がありますので、ケアマネジャーに相談してみましょう。
4. 経済面:公的制度を賢く利用
在宅療養では、介護サービスの利用料や福祉用具の購入費、住宅改修費など、これまでになかった費用が発生することがあります。医療費に関しては高額療養費制度、介護サービス費に関しては高額介護サービス費といった公的制度を活用することで、負担を軽減できます。 これらの制度について、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。
5. 精神的な負担:SOSを出せる環境づくり
介護を続ける中で、社会からの孤立感、仕事や家事・育児との両立への悩みなど、精神的な負担は避けられません。ショートステイなどの社会資源を利用したり、介護休暇などの制度を活用したりすることも有効です。 また、家族や友人、ケアマネジャーなど、つらい気持ちを打ち明けられる関係性を築いておくことが重要です。辛い時に「つらい」と言える環境を整えておきましょう。
6. 社会資源の活用:フォーマル・インフォーマル両面から
訪問介護や訪問看護といったフォーマルな社会資源の利用は、ケアマネジャーに相談するのが近道です。 一方、インフォーマルなサービスとして、地域の公民館などで開催されている認知症カフェや相談会なども役立つ場合があります。自治体のホームページなどで情報を探してみましょう。疾患別の患者会や家族会に参加することで、より具体的な情報や支援につながることもあります。
◆常にアンテナを張り、負担の少ない療養生活を
在宅療養は、ご本人だけでなく、ご家族にとっても大きな転換期となります。医療や介護に関する情報を常に収集し、利用できる制度やサービスを把握しておくことで、いざという時に慌てず、より負担の少ない療養生活を送ることができるでしょう。